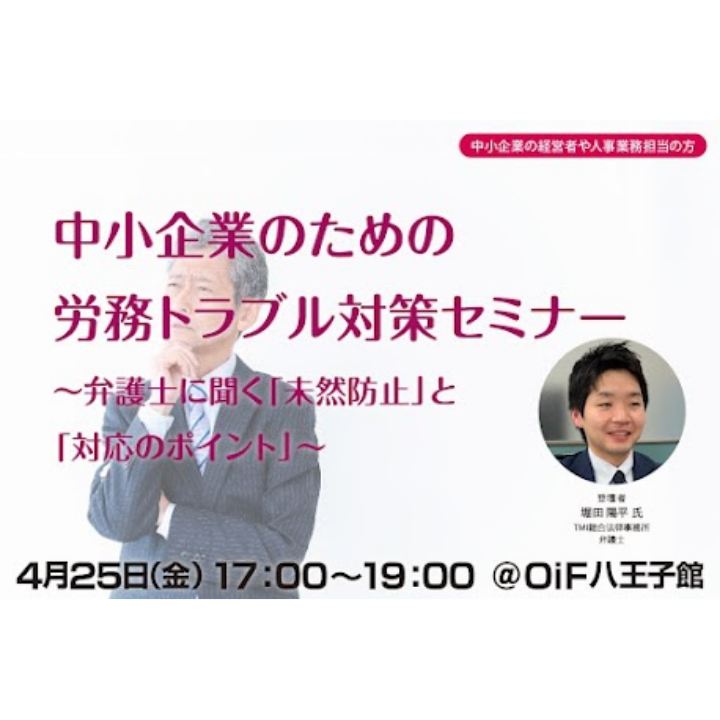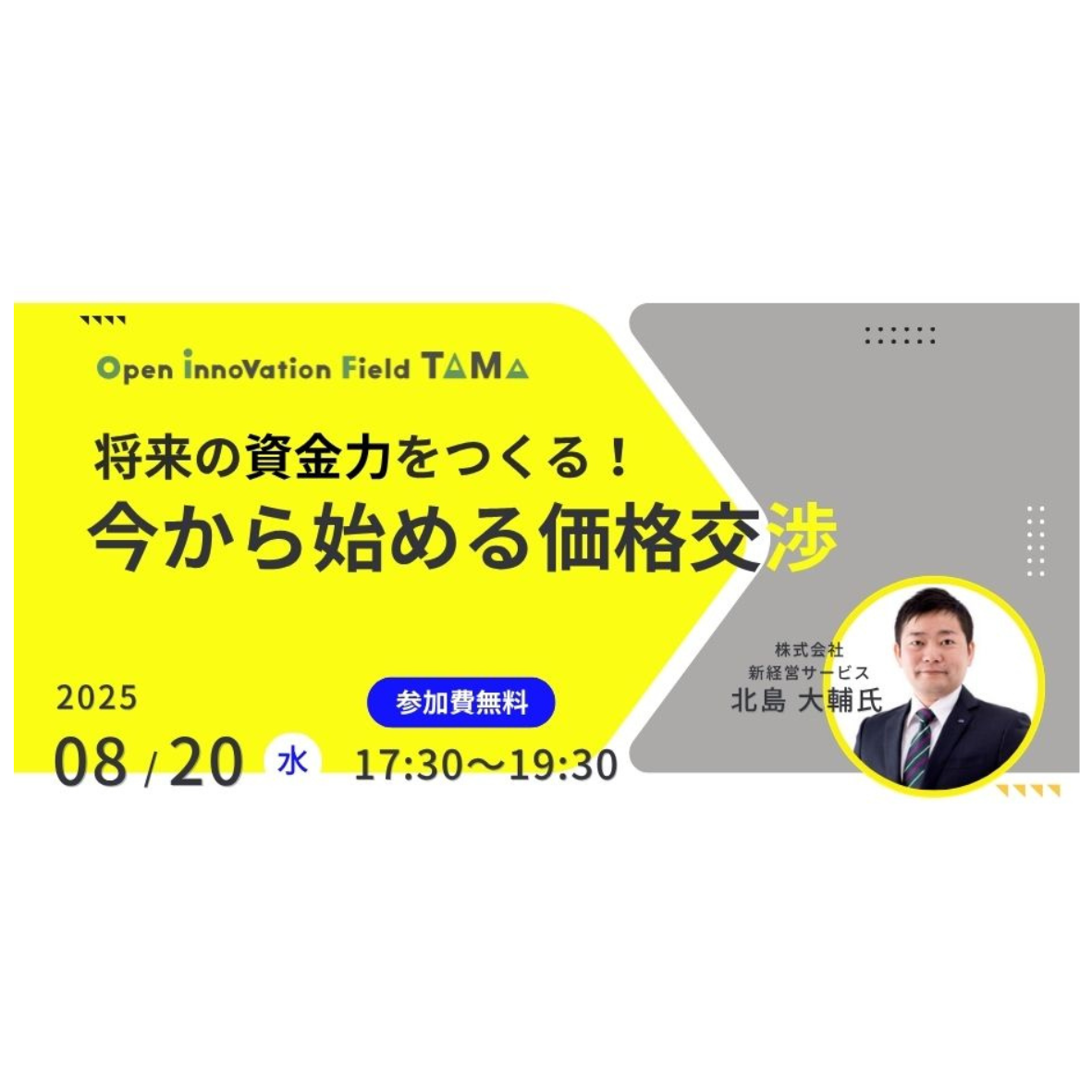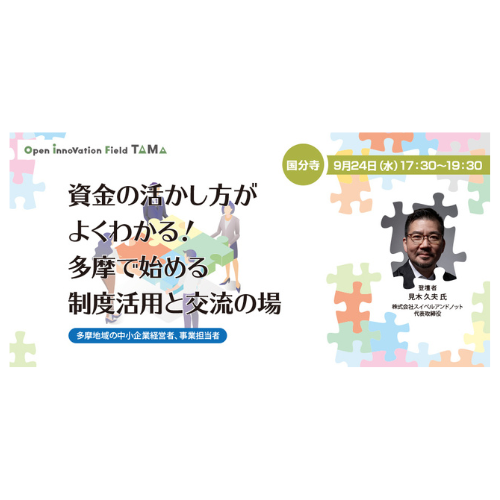はじめに
4月24日(火)にOiF八王子館で実施したイベントの内容をお届けしています。
気になっていたけど申し込めなかった、OiFってどんなイベントをやっているのかなど、ご興味のある方は是非ご一読ください。
様々な業界で人手不足が叫ばれる昨今、福利厚生の充実は良質な人材を集めるために重要な要素になっています。今回のセミナーはマネー・マネジメントFPオフィスの代表、資産運用のプロフェッショナルである前田さんをお招きし、中小企業の経営者・人事担当者の方々向けに、確定拠出年金の基本から導入のメリット・デメリット、運用のポイントを解説いただきました。
1.確定拠出年金の特色
確定拠出年金は、将来の年金受給額を自身の運用成果に委ねる資産形成の仕組みです。確定拠出年金制度を導入する背景には、人手不足対策として福利厚生を強化したい企業ニーズと、少子高齢化による公的年金への不安があります。
1-1 企業型DCの拡大状況と特徴
企業型DCは企業が掛金を拠出し、従業員が運用商品を選ぶ制度です。2024年3月末には加入者約830万人になるなど、急速に拡大しています。
企業型DCの特徴としては以下の通りです。
• 商品ラインアップ:元本確保型(定期預金・年金保険)から、リターン重視の株式型・債券型・バランス型投信まで多様で、3本~35本を自由に組み合わせることによりリスク許容度に応じた運用が可能
• 運用の柔軟性:毎月の掛金配分や金額はいつでも変更でき、市場の変動やライフプランに合わせて設計、転職・退職時には資産を他の企業型DC、企業年金基金、中退共へスムーズに移すことが可能
• 受給・拠出年齢:受給開始は60歳以上(勤務期間10年未満は65歳以上)、掛金拠出は70歳まで、運用指示は75歳まで
1-2 iDeCoの特徴
iDeCoは個人が自ら掛金を拠出する制度で、2024年3月末の加入者は約360万人、資産残高は6,200億円に達しています。口座は自分で開設し、給与天引きや銀行振替で拠出可能です。商品ラインは企業型DCとほぼ共通で、預貯金・保険・投信の中から3本~35本を選択します。
iDeCoの特徴は以下の通りです。
• 自律的運用:掛金の変更や商品の入れ替えが随時可能、運用コストや手数料を比較しながら自分に最適なポートフォリオを組める
• 移管制限と併用:企業型DC加入者は、iDeCo口座へ資産を移管できますが、iDeCo資産を企業型DCへ移すことはできない、複数制度の併用で税制優遇を最大化
1-3 両制度の税制優遇
どちらの制度も、拠出時の所得控除、運用益非課税、受取時の控除適用という三重の税制優遇を受けることができます。年間数万円~数十万円の税負担軽減効果がある場合もあり、税制におけるメリットは導入判断の重要なポイントです。
2.企業・従業員視点におけるメリット・デメリット
企業側の視点
企業側としては確定拠出年金を導入するコストや事務作業の手間など短期的なデメリットはもちろんありますが、長い目で見ると節税対策、人材の定着にも繋がります。
• メリット:社会保険料軽減(掛金が計算対象外)、制度費用は全額損金算入、福利厚生充実で採用力・定着率向上に
• デメリット:導入・運用準備に約半年、初期費用(事業所20万円+加入者1名5,000円)、年間運営費、入退社手続き費、投資教育コストが発生
従業員側の視点
従業員側から見ても、所得税控除などの節税になる他、投資をより自分事にすることができます。元本割れのリスクを負う必要はあるので、商品の運用によってリスクの分散を図るなど工夫が必要です。
• メリット:掛金が所得控除対象、運用益非課税、受取時控除適用、無料投資教育でスキルアップが期待できる
• デメリット:運用リスクによる元本割れ可能性、最短60歳まで資金拘束、社会保険料控除に伴う厚生年金減少リスクのおそれがある
導入の際はこれらのメリット・デメリットを比較し、自社・自分に合った制度設計をすることが大切です。
3.制度導入のステップ
制度を導入する際の具体的な流れをご紹介します。
1.機関選定:運営管理・資産管理・商品提供機関を資産残高、サポート体制、手数料で比較し、選定します
2.制度設計:従業員ニーズと企業負担のバランスを見て、選択制、上乗せ型、併用型、マッチング拠出から選択します
3.コスト試算:初期20万円+加入者5,000円、年間同額、入退社ごとに5,000円が掛かります
4.運用サポート:定期的に投資教育・運用報告を実施し、従業員の理解と継続運用を後押しします
また、イメージとして確定拠出年金制度導入後のスケジュール例を紹介します。
あくまでひとつの例ですが、制度開始までは半年程度の準備期間が必要です。
導入スケジュール例
• 2024年9月:社内説明・書類準備(社内合意形成、就業規則改定、必要書類収集)
• 2024年12月:従業員説明会の開催・労使合意
• 2025年1月末:厚生労働局への申請書提出
• 2025年3月中旬:加入者登録および給与明細改定
• 2025年4月1日:制度開始
まとめ
確定拠出年金は、自社の福利厚生強化と従業員の老後資産形成を両立させる制度です。データと具体的フローを押さえ、自社に合った機関等を選定することはもちろんですが、導入後の従業員へフォローをすることも継続的な運用には重要です。投資に関する学びは経済や他の企業を調べるきっかけにもなり、従業員一人一人が知識をつけることにも繋がります。 福利厚生の充実から、従業員が自ら学び、気持ちよく働ける環境整備を目指してみませんか?
マネー・マネジメント FPオフィス 代表
前田 敏 氏
■経歴
- 同志社大学卒業後、三洋投信、インベスコ投信にてファンド・マネジャー、トレーダーとして株式、債券、為替の運用・売買業務を幅広く経験。
- その後、アクサ・インベストメント・マネジャーズでは大手の銀行、生損保に対してヘッジ・ファンドの販売業務を、三菱UFJアセットマネジメントでは一般投資家、金融機関の販売員向けにセミナー講師を担当 2021年8月に資産運用専門ファイナンシャル・プランナーとして独立開業。
- 資産運用を通じて投資家のみなさまの生活をサポートしている。
https://mmfpo.com/(外部サイトへアクセスします)
今後もOiFでは、様々な内容のセミナー、イベントを企画してまいります。皆様のご参加をお待ちしております。