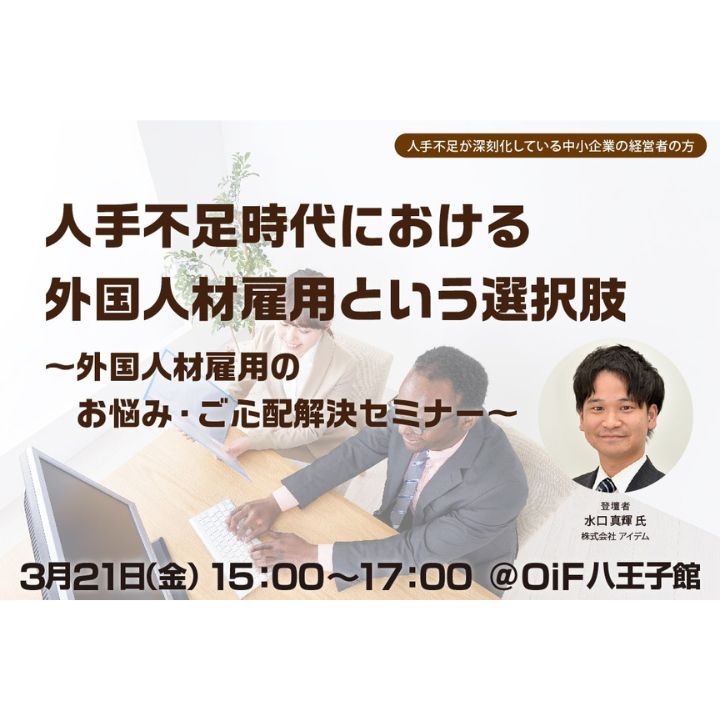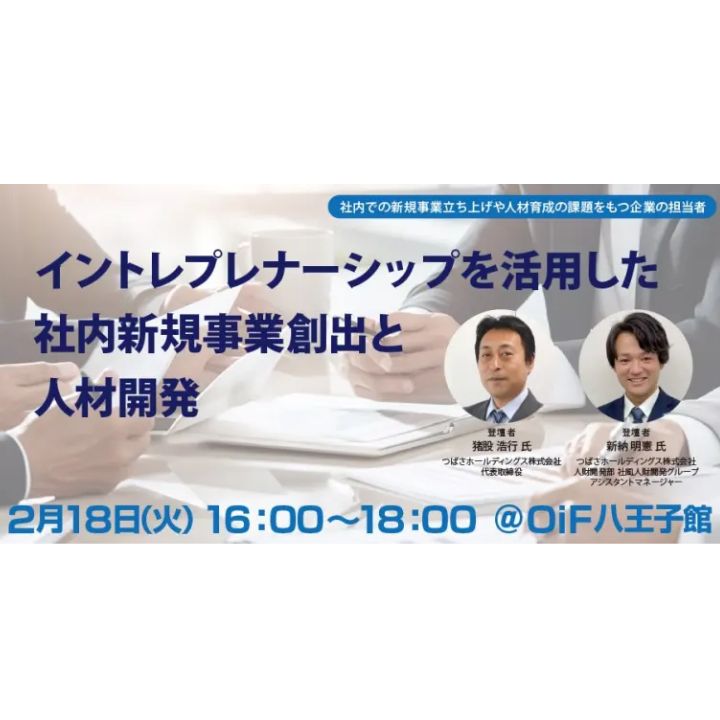2025年3月21日、オープンイノベーションフィールド多摩 八王子館にて、中小企業の人手不足課題を解決するためのセミナー「人手不足時代における外国人材雇用という選択肢〜外国人材雇用のお悩み・ご心配解決セミナー〜」を開催いたしました。
本記事では、イベントの内容をわかりやすくレポートいたします。外国人材の採用や、育成に興味のある方は是非ご一読ください。
はじめに
本セミナーでは、外国人材採用支援の実績を多数持つ株式会社アイデム グローバルグループの水口正樹氏をお招きし、外国人材を受け入れるにあたっての必要な基礎知識から、採用時の実務、ベトナムとの連携事例、実際のインターンシップや採用まで、具体的な事例をご紹介いただきました。
1. なぜいま「外国人材」なのか?―人手不足の現実と人口構造の変化
まず外国人材の受け入れがなぜ必要なのか。今、日本社会が直面している構造的な課題、すなわち「少子高齢化」による生産年齢人口の減少について改めてお伝えしていきます。
総務省のデータによれば、日本の人口は2008年をピークに減少傾向にあり、今後40年間で約3,000万人の人口が減少し、2065年には総人口が9,000万人を下回る見通しです。65歳以上の高齢者が全人口の4割を占めるとも予測されており、まさに「超高齢化社会」が進行しています。
中でも、生産年齢人口(15歳〜64歳)の減少は企業活動に深刻な影響を及ぼします。労働力の供給源が縮小する中、事業継続や技術承継の面でも課題が顕在化しています。
一方で、外国人労働者の数は右肩上がりで推移しています。2023年時点で日本に在留する外国人は340万人、そのうち労働者は約230万人。これは過去最高を記録しており、今後も特定技能制度などを通じてさらに拡大が見込まれています。
「外国人材は今や“選択肢”ではなく“必然”に近い」と言える状況になりつつあります。
2. 在留資格の基礎知識―知らなければリスクになる制度の理解
外国人を雇用するにあたって、最も重要でありながら誤解されやすいのが「在留資格」の問題です。在留資格を正しく理解し、適切に運用しないと、不法就労や不法滞在といった重大な法令違反につながってしまう可能性があります。
29種類ある在留資格の中から、企業が特に知っておくべき以下の4つを紹介します。
1. 技術・人文知識・国際業務(通称:技人国):学士以上の学位を有し、専門知識を活かした業務に従事する外国人が対象。
2. 特定活動:インターンシップや文化活動など、個別に定められた活動に限って就労が許可される。
3. 特定技能:2019年に新設された制度。16の分野で一定の技能を持つ人材が対象。
4. 技能実習:開発途上国への技術移転を目的とした制度。現在は制度見直しが進行中。
中でも「技人国」は理工系の優秀な人材を正社員として採用する場合にもっとも一般的であり、受け入れ企業にとっては制度理解と準備が求められる在留資格です。
「技人国」は専門分野と業務内容が一致していないと、許可が下りない場合があります。特に工場作業などの単純労働には「技人国」資格は使えないため注意が必要です。
3. 人材確保のためのターゲットの考え方
理工系外国人材の採用は、“数が少ない”だけでなく、“言語の壁”も課題となる場合があります。
理系人材で日本語力がある外国人は限られており、確保には戦略的なアプローチが必要です。
採用ターゲットは基本的に大きく以下の3つに分類されます。
(1) 日本国内の外国人留学生(新卒)
既に日本に滞在しており、文化や生活習慣に慣れているが、日本語力や理系比率にばらつきあり。
(2) 日本国内で既に就労中の外国人(転職者)
実務経験があるが、競合他社との採用競争が激しい。
(3) 海外現地の大学生(新卒)
現地の理工系大学と提携し、教育された人材を直接採用するルート。
特に(3)は、競合が少なく、理工系トップ大学との提携により優秀な層を確保しやすいと言えます。この場合は言語や文化の違いを前提に、日本語教育と事前研修をセットで提供することがスムーズな受入れのために重要です。
4. ベトナムとの連携事例―“即戦力人材”を育てる仕組み
即戦力人材を育てる取り組みとして、「ハノイ工科大学」との共同教育プログラムの取り組みについて紹介します。
ベトナム屈指の理工系大学と提携し、在学中の学生を対象に2年間・1000時間以上の日本語とビジネスマナーの教育を実施。日本語能力試験(JLPT)N3相当の語学力と、日本文化への理解を併せ持つ人材を輩出しています。
この取り組みは、日越外交関係樹立50周年記念事業にも認定されており、制度的な信頼性も高く、地方自治体との協定事例も多数。実際に神奈川県とは地域包括連携協定を結び、インターンシップや人材紹介を通じた地域経済の活性化にも寄与しています。
このようなプログラムに参加する学生は“どんな経験が得られるか”を重視することが多く、企業規模や福利厚生についてアピールするよりも、業務内容やキャリア成長の可能性を示すことが必要です。
5. インターンシップのメリット
「インターンシップ」は外国人材雇用のための現実的な第一歩です。
当社が他社と連携して行っているインターンシップは、短期(1週間)の「体験シップ」と、3ヶ月〜1年の「中長期インターンシップ」の2形態があります。2024年には、神奈川県綾瀬市との連携により、ベトナムの学生11名を招聘、うち4名は市内企業でCAD設計や現場研修を体験しました。
体験シップでは、来日前に日本語・ビジネスマナー研修を行い、来日後は電車の乗り方やお金の使い方まで実践的に学ぶ事前研修を実施しました。受け入れ企業からは「非常に飲み込みが早く、現場にもすぐに馴染んだ」と高評価を得ています。
発表会や観光プログラムも組み込まれており、学生・企業双方にとって満足度の高い経験となっています。
6. 採用事例の紹介―中小企業でも十分に活用可能
外国人材を実際に受け入れた企業はどのように採用を進めてきたのか、中小企業における成功事例も紹介いたします。
• 茨城県の従業員35名の製造業企業
理工系の日本人採用に苦戦したが、ハノイ工科大学との連携で学生1名を3ヶ月のインターンを経て採用。現地面接と体験を通して人柄とスキルの両方を確認することができた。
• 神奈川県の従業員52名のIT関連企業:
初の外国人採用に挑戦。オンライン交流会と現地訪問を通じて学生と信頼関係を構築。7月にはインターンシップとして3名を受け入れ予定。
いずれの企業も大きな規模の企業ではありませんが、優秀な外国人を採用するための取り組みが実現できています。
受け入れ体制と育成意欲があれば、企業の規模や社格に関係なく、熱意がある外国人を育成することができます。
7. まとめ
今後ますます労働力人口が減っていく中で、“外国人材を受け入れるかどうか”を考えるのではなく、“どのように受け入れるか”が企業の競争力を左右します。インターンから始めてみる、制度を理解する、小さく試してみる。その一歩を踏み出すことができれば、10年後の持続可能な人材採用の手法を育むことに繋がっていくと考えています。
本セミナーを通じて、外国人材の受け入れは“リスク”ではなく“未来への投資”であるという視点を学んでいただくことができたのではないでしょうか。外国人材採用に対する漠然とした不安や誤解を払拭し、行動につながる学びの機会となった本セミナー。人手不足に悩む多摩地域の中小企業にとって、外国人材の受け入れが有力な選択肢のひとつになっていれば幸いです。
株式会社 アイデム
水口真輝 氏
- 大学卒業後、エンジニア専門の人材会社へ入社し、人材紹介業務を通じて、大手企業から中小企業に至るまで幅広い顧客の課題解決に取り組む。
- 在職中にはトップセールスを幾度となく達成し、入社半年後にはリーダーに昇進。
- 3名のチームメンバーのマネジメントを任され、リーダーシップを発揮。 加えて、未経験者・経験者を問わずエンジニア採用の“面接官”として数多くの候補者と向き合い、企業にとって最適な人材とのマッチングに貢献。
- 自身が支援するコンサルティング会社において、15名のエンジニア社員のメンター業務を担当。キャリア形成やスキル向上を支援することで、個人と企業の成長を促してきた。
- 現在はその経験を活かし、株式会社アイデムにてベトナムをはじめとする理工系外国人人材の就職支援を行っている。
今後もOiFでは、様々な内容のセミナー、イベントを企画してまいります。皆様のご参加をお待ちしております。